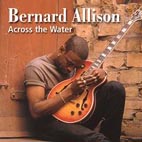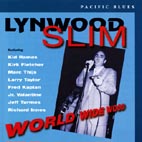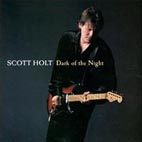去る3月、交通事故により突如帰らぬ人となってしまったキング・アーネスト。彼が死の1ヶ月前に完成させていた遺作が、リリースとなった。 亡くなった時点で61歳だった彼だが、アルバムは97年の"King Of Hearts"と本作の2作のみである。レーベルがファット・ポッサムというのは意外だったが、内容にはその影響はないようで、彼らしい落ち着いたタッチに仕上がっている。スロー・ブルース、バラードを中心とした選曲に派手さはないが、彼の歌を堪能するには申し分ない。スロー・ブルース1での重圧感、マイナー・キーの3での声を裏返らせての熱唱など、実に彼の歌は表情豊かだ。ソウル・ナンバーの4や8などでは、温厚な人柄が滲み出ているのが、心を打たれる。特に哀愁を帯びた8は、名曲だ。カヴァー曲が多かった前作と違い、今回は半数がオリジナル曲で、そこからも力の入り具合を窺い知ることができる。 本作の次はゴスペル・アルバムを作ると言う話もあったそうで、前向きに活動していた最中の死が惜しまれる。(1/5/2001)
プレイボタンを押して、出てきた音に「これってゲイトマウスの新作?」と思っても不思議ではない。キッド・ラモスの3作目となるアルバムの冒頭を飾るTボーンのインストで、最初のソロを取るのは、ゲスト参加のゲイトである。そういえば、彼もこの曲をカヴァーしてたっけ。ここには、他デューク・ロビラードも加わり、3人によるノリノリなジャムを展開している。アルバム全体の印象もそんな感じだ。タイトルが示す通り、賑やかなパーティーといったおもむきとなっている。リトル・チャーリー、キム・ウィルソン、ラスティー・ジン等々、多彩なゲストを迎えて、ジャンプ・ナンバーを次々と繰り出す楽しい内容で、しっとりしたりする部分は全くない。ラモス本人はヴォーカルを取らない(ゲスト陣が入れ替わりで歌っている)こともあり、特段目立っているわけではないが、職人的なギター・ワークはさすがと思わせるものがある。ところで、肝心のファビュラス・サンダーバーズって、ツアーはしてるけど、アルバムはもう出さないの?(1/5/2001)
昨年暮れの来日時に「帰国したら新作のレコーディング」に入る、とバーナードは言っていたが、その新作が届けられた。トーンクールに移籍してから初のアルバムとなる。 かなりロックっぽくなってきたな、というのがまず率直な印象だ。前作も多様な音楽性を盛り込んではいたが、でもまだブルースを出発点において発展させた感じに聞こえた。それに対してこの作品では曲のスタイルとしては、ストレートなブルースは殆どなく、パンチの効いたロック、ファンク的なものが目立つ。最近のライヴでも、彼はかなりそういう路線を前面に出しているようなので、自然な成り行きと言えるかもしれないが、ライヴの方がもっとブルースしていたな、と思った。でも、それが悪いというわけでは全然なくて、作品としてよくまとまったものになっていると思う。ジョニー・ウィンターそっくりなスライドを披露した7、スティーヴィー・レイ的なソロを弾く11などは、バーナードが彼らに強く影響を受けていることを改めて感じさせる。(1/5/2001)
もう10年以上前のことだが、LAでロイ・ゲインズのライヴを観た際に、ゲストでこのミッキー・チャンピオンが登場したことがあった。馴染みのない名前だったが、そのダイナミックな歌声はかなりのインパクトがあり、以来ずっと気になっていたのだった。50年代にモダンなどいくつかのレーベルに録音があり、またジョニー・オーティス・ショーの歌手としてツアーをした経験も持つ彼女だが、アルバムとしてはこれがデビュー作となる。LAのクラブ、ベイブス&リッキーズ・インで昨年録音されたライヴ盤だ。バンドのスタイルや選曲が少々ジャズっぽいところは、ルース・ブラウンに近い感じだが、歌はもっとシャウトしているし、声質はまったりした感じでダイナ・ワシントンを彷彿させる。1、3などアップテンポ曲での強力な歌声、ジョニー・オーティス・ショーの5でのダーティーな感じなど、歳はかなりいってるはずだが、メチャクチャ活きがいい。惜しむらくは、1曲がやや長めで、ダレること。次回は、よく練ったスタジオ盤を是非作ってほしい。(1/5/2001)
ロサンジェルス出身のリンウッド・スリムは、30年以上の活動歴を誇るハーピスト。影響を受けたプレイヤーとしては、リトル・ウォルター、チャーリー・マッスルホワイトを挙げているが、音楽性としては彼らより、スウィング色が強いのが特徴と言えるだろう。前号で紹介された"Blues Across America - Los Angeles Scene"では、プロデューサーも務めている。 新作のタイトルは、Worldwide Webに引っかけたものだろうが、数年に渡って録りためた世界のミュージシャンとの共演を1枚のCDにした格好だ。決して派手さはないのだが、気持ちよくスウィングしたアルバムである。ハープのプレイとしては、テクニックを披露したジャズ色のインスト8.などもよし、またマジック・サムのカヴァー10.あたりで聴かせるバッキングも得難いものがある。カナダ、イタリアでのセッションなどもあるが、やはり中心となるのは、地元LAでのもの。LAの若きギタリスト、カーク・フレッチャー(現在24歳)の切れのいいギターも要注目だ。(8/25/2000)
スモーキン・ジョーとブノイスの2人がバンドを組むようになってから約10年、通算7枚目となるアルバムをリリースした。テキサスらしいパワフルなギターを押し出したロック的なサウンドを基調とする彼らだが、攻めっぱなしにはならないのがいいところ。これまでの作品でも、美しいバラードでじっくり聴かせるなどして、音に幅を持たせて楽しませてくれた。 本作でも基本的には、彼らの持ち味は変わらない。ただ、攻撃的な面はいくぶん控えめで、よりじっくり聴かせる音になっているように思う。ストレートなブルースではマイナー調の9.、シャッフル・インスト11.あたりがよい出来だ。リフなどにロックっぽいひねりを入れたものも多いが、さほどロック色は強くない。ちょっと変わり種は(1)。今や懐かしいトークボックスを効かせたギターでリフを作っていたりして、面白かった。無機質な歌い方がZZトップっぽかったりもする。SRVファンには激しいボ・ディドリー・ビートの9.がお薦め。ギターにここぞとばかり、力が入ってます。(8/25/2000)
待ってました!スウェーデンから届いたシリーズ第二弾。本シリーズの背景などについては、"Volume One"の紹介文を見てほしい。"Volume One"のリリースから1年近く待たされたが、内容を聴けば待った甲斐があったと思うだろう。 ポール・バターフィールドのバンドは、レコード・デビュー前の演奏で、初レコーディングという貴重なもの。演奏は、彼らからすれば控えめだが、まったり濃いブルースを聴かせてくれる。このシリーズの他のトラックにはちょくちょく顔を出しているマイク・ブルームフィールドは、まだバターフィールドのバンドには参加しておらず、ギターはリトル・スモーキー・スマザーズが弾いている。彼のプレイはコードワークのクールさが印象に残った。6くらいは勢いをもう少し爆発させてくれたら、と思わなくはないが、レコーディングの場所がちゃんとしたスタジオでなく休業中のバーであったことと、他のアーティストが弾き語り中心であったことから考えれば、フルバンドで収録出来ただけでもありがたいというべきであろう。 個人的には、一番聴きたかったのが、ウォッシュボード・サム。戦前にビッグ・ビル・ブルーンジーと活動し、ほんわかした味の楽しいブルースを沢山残したサムだが、戦後は事実上引退していたので、音はあまり残っていない。そういう意味で貴重なレコーディングなのだ。またバターフィールドがファースト・レコーディングならば、ここでのサムはラスト。このセッションの後まもなく彼は体調を崩し、66年にこの世を去っているのである。さすがに、戦前のレコーディングに於ける声の瑞々しさはないが、彼らしいすちゃらか、すちゃらか、と刻むウォッシュボードは健在で、聴けて幸せ、と言う気分になった。ウォッシュボードの音がクリアに臨場感をもって聞こえるのも嬉しい。これは戦前録音にはなかったことだ。ビッグ・ビルこそいないが、ピアノのブラインド・ジョン・デイヴィスが好サポートぶりを聴かせる。因みに、このセッションでは、サムの名曲"Mama Don't Allow"もレコーディングされているようだが、ここには入ってないのが、ちょっと残念。 続くジョン・リー・グランダーソンとエイヴリー・ブレイディーは作品が少なくあまり知られていないが、ブレイディーはテスタメントの"Sounds of Delta"に収録されてたりもする。グランダーソンはデルタ・スタイルの弾き語りで、ギターのリズムの小気味よさが光る。特に"Rollin' And Tumblin'"調の16は聴きものだ。ブレイディーは彼に較べるとタッチは軽く、トラディショナルな雰囲気の中にも洗練されたものを感じる。 2枚目は、リトル・ブラザー・モンゴメリーの演奏で幕開けだ。彼のピアノは、哀愁を帯びた甘口なタッチが持ち味だと思うが、ここでもその魅力は健在だ。ちょっとしゃがれた歌も魅力たっぷり。アーヴェラ・グレイはレッドベリーを彷彿させるフォークソング的な世界を披露。歌、ギターともに清々しさを感じさせる勢いがある。特に7分以上に及ぶ6は、熱演と呼ぶに相応しい。マックスウェル・ストリートのミュージシャンの演奏を収録したドキュメンタリーCD"And This Is Maxwell Street"にも、彼の同曲の演奏が収録されているので、聴き較べるのも面白い。ギターの音色がかなり違っている。 最後は、セントルイス・ジミー(オーデン)。代表曲の"Going Down Slow"はやってないが、11はその改作となる曲だ。彼はヴォーカルのみで、バックの演奏はサニーランド・スリム(piano)、ウォッシュボード・サム(washboard)、マイク・ブルームフィールド(guitar)が担当。中では、特にスリムの演奏が光る。本人の歌は地味で、歌い方にもメリハリはないのだが、もっちりした声質が得難い魅力を放っている。 さて、次はいよいよシリーズ完結編(メンフィス、ニューオーリンズ)だ。今度は、早く出してね。
3年前、聞いたことのないこのザディコのオヤジのライヴをニューオーリンズのジャズフェスでみてすっかり気に入ったのだが、向こうでアルバムを探したけど、結局みつからなかった。それ以来ずっと気になる存在だったのだが、最近になってこのアルバムが出たというわけ。即買いましたよ! 相変わらず知名度は低いと思うけど、これを聴いてやはりカッコいい!と思った。ボー・ジョック亡き後、僕はこの人に期待をかけたい。新星なんていうには歳食い過ぎてるけど、このノリ、パワーはもっとメジャーに出てきて然るべきと思う。ボー・ジョックを引き合いに出したが、実際ワンコードで押す2.や11.などの曲調は彼に通ずるものがあり、かなり雰囲気は似ている。ガツンと来るインパクトではボーの方が上かもしれないが、内容的に見劣りはしない。ボーよりものんびりした雰囲気がこの人の味となっている。クリフトン・シェニエのバラード5.なんて胸に染みますよ。 もっとアルバム聴きたいな...。早く次のをだしちくりぃ。気が早い?(2/22/2000)
「シカゴからブルースマンを奪うことは出来ても、ブルースマンからシカゴを奪うことは出来ない。」というMCがカッコいい。70年代にパリに移住したルーサーだが、本質は一貫しているということだろう。故郷シカゴに戻ってのライヴで、彼はいつもの勢いで弾けまくっている。直球勝負の彼のサウンドは、すかっと気持ちいい。ギターで喋ったりする芸人ぶりも堪能できる。1枚目の最後に入っている、ラッシュ、キャンベルとのセッションもおいしすぎるよぉ!超満腹の2枚組だ。(2/22/2000)
バディー・ガイのギタリストとして活躍するスコット・ホルトのソロ・アルバムだ。バディーのライヴでなかなか芯の通ったプレイを聴かせていたので、その存在を気にしていた人も多いのではないだろうか。彼は97年に『Messing With The Kid』というアルバムを出しており、本作は2作目となる。自らのバンド他、ダブル・トラブル、ジミ・ヘンドリックス・バンドのメンバー(ミッチ・ミッチェル、ビリー・コックス)がバックに付き、プロデューサーにはやはりジミとの仕事で知られるエディー・クレイマーを迎えた。となるとジミばりのハード・ロック炸裂か、と言うとそうでもない。攻撃的なプレイもあるが、全体的にいうと抑えめ、という印象を受ける。ジミの(9)を始め、プリンスの(1)、そしてクラッシュの(2)など、カヴァー曲はブルースから外れたものが多いのだが、違和感はない。ピュアなブルースかと言えば違うかも知れないが、ブルース魂はしっかりと生きている。バディー参加の(6)は、大ギター・バトル大会で、ギター・ファンは大満足だろう。(2/22/2000)
過去のレビュー
Text by Masahiro Sumori unless otherwise noted. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||